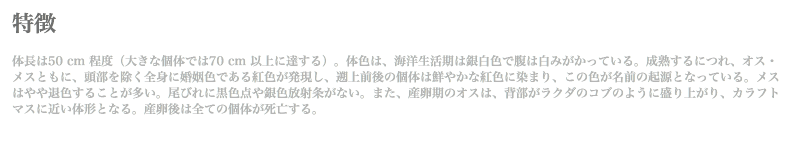紅鮭を追い求めて

Ecology
自然分布する降海型の個体は千島列島・カムチャツカ半島からカリフォルニア州コロンビア川以北の北緯40度以北の北太平洋・ベーリング海・オホーツク海に棲息する。水温が低下する冬期は南部に移動し、水温が上昇する時期は北部に移動する。千島列島側では択捉島ウルモベツ(得茂別湖)湖が降海の生息南限とされる。


日本では北海道の阿寒湖にベニザケの河川残留型(陸封型)であるヒメマスが天然分布し、択捉島を除き降海型のベニザケは分布していない。海洋での生息適水温は約3℃から13℃で、上限塩分濃度は33.46psuと狭い。遺伝的には、3グループに分けられる。択捉島のSopochnoye 湖産と支笏湖産では遺伝的類似性が乏しい。
自然の状態での降河はシロサケとは異なり、孵化・浮上した年には降海しない。ギンザケやマスノスケの様に河川の上流で生まれた個体は途中の湖などで1年から数年ほど過ごし、8cm - 15cmに成長し春にスモルト化した個体が降海するが、早熟なオスでは短期間(1年未満)の淡水生活の後降海するものや、河川或いは河口域に留まる個体もいる。そのため、産卵・繁殖するための河川には途中に湖沼がある場合が多い。生まれた河川に戻る母川回帰性はサケ類中でも強く、生まれた支流まで正確に突き止めて遡上する。成熟にかかる期間は1 - 4年ほどで、7月 - 12月に産卵のため生まれ育った河川へと遡上する。海洋での回遊範囲は広い、主な餌は動物プランクトンで、特にコペポーダやオキアミ類などのプランクトン性の甲殻類を中心に摂食するが、アラスカ湾ではヒメドスイカなどのマイクロ・ネクトンもよく摂餌する。サケ類の中ではプランクトンを漉し取る鰓耙の数は突出して多い。

折居健二 KenjiOrii
動植物全般を独特の視点で撮らえる写真家として活躍しています。その活動は希少絶滅危惧動物全般に及んでおり、近年では動植物の繁殖にも興味を持ち行動している。(研究実績)オガサワラオオコウモリ、イリオモテヤマネコ、世界最大の蛾ヨナグニサン、アカウミガメ、アオウミガメ、ヤンバルクイナ、ナキウサギ、コノハズク、等多数に及んでいます。1969年1月生まれ 札幌市出身